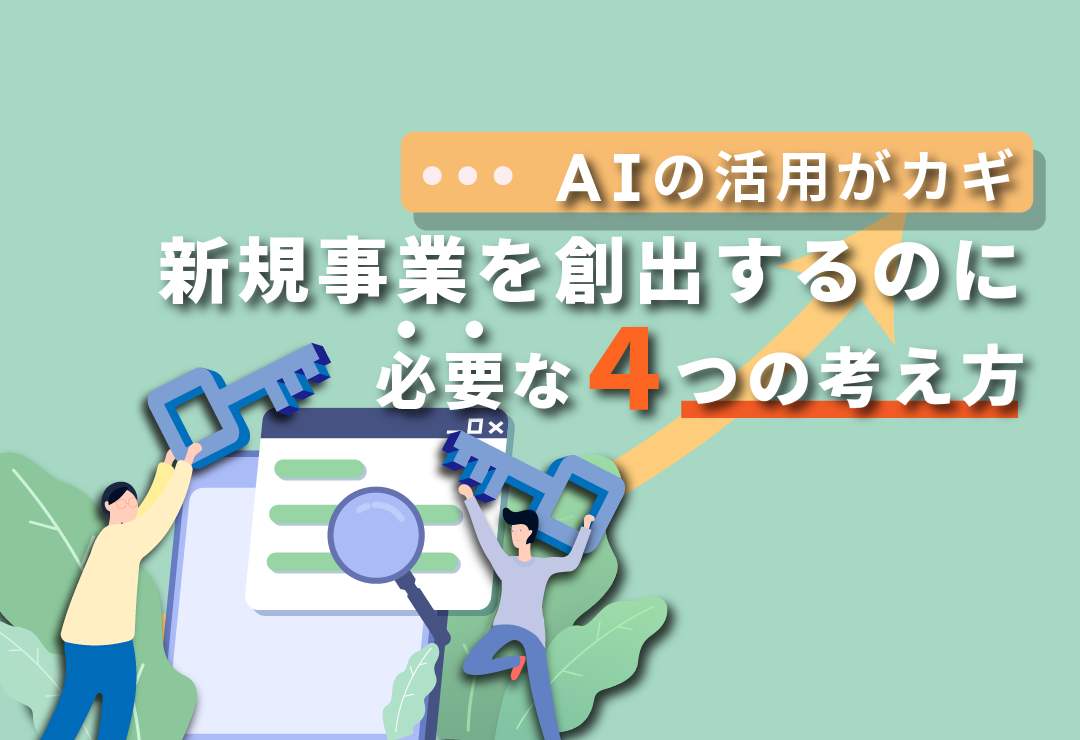目次
なぜかユーザーが定着しない…その悩み、「オンボーディング」が原因かも?

「鳴り物入りでリリースした新サービス。でも、アクティブユーザーが全然増えない…」
プロダクトマネージャーやデザイナーなら、一度はこんな悩みに頭を抱えたことがあるんじゃないでしょうか。実はその原因、機能や見た目の問題ではなく、ユーザーがサービスを使い始める最初の5分間の体験、つまり「オンボーディング」にあるのかもしれません。
こんにちは!私たちpicks designは、見た目のデザインだけでなく、その裏側にある「体験」を設計することで、事業成長をサポートするデザインカンパanyです。
この記事では、多くの競合ブログが語るような「きれいなUI事例集」で終わるつもりはありません。私たちが実際のプロジェクトで、どのようにユーザーの課題を掘り下げ、ビジネス成果に繋がるオンボーディングUIを設計しているのか。その泥臭い思考プロセスを、具体的な事例を交えながら余すことなくお伝えします。単なるテクニックではなく、「考える技術」を持ち帰ってください。
そもそも、なぜオンボーディングがビジネスの死活問題になるのか

「オンボーディングって、要はチュートリアルでしょ?」もしそう考えていたら、非常にもったいない!優れたオンボーディングは、ユーザーの離脱率を劇的に下げ、LTV(顧客生涯価値)を最大化する、ビジネスの心臓部とも言えるパートなんです。
ユーザーはあなたのサービスの全機能を理解したいわけじゃありません。「自分の悩みを、いかに早く、簡単に解決してくれるか」だけを知りたいのです。
しかし、多くのサービスがここでユーザーの期待とすれ違ってしまいます。よくある失敗パターンは、こんな感じです。
- 機能の押し売り: 「こんなにすごい機能があるんです!」と一方的に説明してしまう。
- 専門用語のオンパレード: ユーザーが知らない社内用語や業界用語で混乱させる。
- 出口のないチュートリアル: スキップできず、いつ終わるかわからない説明を強制する。
作り手の「全部知ってほしい」という想いが、ユーザーの「早く価値を知りたい」というニーズを置き去りにしてしまう。この最初のすれ違いが、致命的な離脱を生むんです。だからこそ、私たちはUIを設計する前に、まずユーザーの心理を深く理解することから始めます。
成果を出すデザインは「プロセス」が9割。私たちの思考の全ステップを公開
では、具体的にどうすれば「ユーザーが辞めない」オンボーディングを設計できるのか。僕たちpicks designが最も大切にしているのは、いきなりデザインツール(Figmaなど)を開くのではなく、その前段階にある体系的な思考プロセスです。闇雲にUIを作り始めても、それはただの「勘」に頼ったギャンブルになってしまいますからね。(そもそも、良いオンボーディングを作るための土台となるUI/UXデザインの基本原則については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ最初に読んでみてください)
私たちが実践している思考プロセスは、大きく分けて以下の4ステップです。
| ステップ | 主な活動内容 | このステップの目的 |
|---|---|---|
| 1. 課題の定義と目標設定 | KGI/KPI設定、ビジネス要件の整理 | 何のためにデザインするのか?ゴールを明確にする |
| 2. ユーザーリサーチ | ユーザーインタビュー、データ分析 | 誰の、どんな課題を解決するのか?本音を探る |
| 3. ユーザー体験の可視化 | ペルソナ、ユーザージャーニーマップ作成 | ユーザーの行動と感情を具体的に描き出す |
| 4. 体験設計と情報設計 | Aha Momentの定義、情報構造の設計 | 最短で「価値」を実感させるための道筋を作る |
遠回りに見えるかもしれませんが、このプロセスこそが、ビジネス成果に繋がるデザインを生み出すための最短ルートだと、私たちは確信しています。
Step1:誰の、何を解決するのか? ― 課題の定義と目標設定
デザインプロジェクトの成否は、この最初のステップで決まると言っても過言ではありません。「なんとなく使いやすくしたい」といった曖昧な目的では、絶対に良いデザインは生まれないんです。
まず僕たちがやるのは、クライアントの皆さんと徹底的に対話し、「ビジネスとして、最終的に何を達成したいのか?」を明らかにすること。例えば、「ユーザーの継続率を半年で10%向上させる」といった具体的なKGI(重要目標達成指標)を定めます。そして、そのKGIを達成するために、デザインが貢献できる指標、つまりKPI(重要業績評価指標)に落とし込みます。「初回ログインからチュートリアル完了までの離脱率を5%未満にする」といった具合ですね。
なぜここまで数字にこだわるのか?それは、デザインを「投資」として捉えているからです。かけたコストに対してどれだけのリターンがあったのかを計測可能にすることで、初めてデザインの価値を客観的に証明できる。アートではなく、ビジネスの課題解決。それが僕たちのデザインの出発点です。
Step2 & 3:ユーザーの「本音」を掘り起こし、体験を地図に描く
ビジネスゴールが定まったら、次はいよいよ主役である「ユーザー」と向き合います。データ分析でユーザーの行動を quantitative(定量的)に把握するのも重要ですが、僕たちが特に重視するのは、生の声を聞くユーザーインタビューです。
「なぜ、あの画面で手が止まったんですか?」
「どんな気持ちで、そのボタンを押しましたか?」
こうした問いを重ねることで、データだけでは見えてこないユーザーのインサイト(行動の裏にある本音や動機)が見えてきます。このインサイトこそが、デザインの羅針盤になるんです。
そして、集めたインサイトを基に、具体的なユーザー像である「ペルソナ」と、サービスとの出会いからファンになるまでを描く「ユーザージャーニーマップ」を作成します。これにより、チーム全員が「この人の、この瞬間の、この感情を解決するためにデザインするんだ」という共通認識を持つことができる。机上の空論ではなく、血の通った一人の人間に向けたデザインが、ここから始まります。
Step4:最短で「なるほど!」を届ける ― Aha Momentの設計
さあ、いよいよ具体的な設計のフェーズです。オンボーディング設計で最も重要なコンセプト、それが「Aha Moment(アハ・モーメント)」です。これは、ユーザーが「なるほど、このサービスはこういう風に私の役に立つのか!」と、サービスの核心的価値を初めて実感する瞬間のこと。
私たちの仕事は、このAha Momentをいかに早く、スムーズに体験してもらうかに尽きます。不要な情報を削ぎ落とし、ユーザーが価値を感じるために最低限必要なアクションは何かを考え抜く。機能の一覧を見せるのではなく、実際に手を動かしてもらい、小さな成功体験を積んでもらう。これが体験設計のキモです。
例えば、チャットツールなら「最初のメッセージを送る」、タスク管理ツールなら「最初のタスクを登録して完了させる」。この「最初の成功体験」への道のりをいかにデザインするかが、ユーザーが定着してくれるかどうかの分かれ道になるんです。神は細部に宿る、なんて言いますが、まさにこの部分の丁寧な設計が明暗を分けます。
【事例】私たちの「思考法」を、実際のプロジェクトで追体験
「理屈はわかったけど、実際どうなの?」と思いますよね。ここでは、私たちが手掛けた2つのプロジェクトを例に、思考プロセスがどうUIデザインに結実したかをご紹介します。
ケース1:学習支援アプリのモチベーション設計
就労支援を目的とした学習アプリでは、「学び続ける意欲をどう高めるか」が大きな壁でした。そこで私たちは、単なる進捗バーではなく、歩数計を想起させるメーター型のグラフィックを導入。「学習は、一歩一歩着実に前へ進む旅のようなもの」というメタファーを、インターフェースそのものに宿らせたのです。日々の小さな前進が視覚的に積み上がることで、「明日も続けてみよう」という気持ちをそっと背中から押す体験を目指しました。
ケース2:健康データ管理アプリの負担軽減デザイン
毎日の継続が命となる健康管理アプリでは、ユーザーの負担をいかに減らすかが肝になります。専門的で複雑な医療データだからこそ、あえて情報を徹底的にシンプルに。色とグラフのわずかな変化だけで、ユーザーが直感的に自身の状態をつかめるよう設計しました。アプリを開いた瞬間に「これなら続けられそう」と思える。そのAha Momentを最短距離で提供するための戦略です。
まとめ:オンボーディングは「おもてなし」。さあ、あなたのサービスで実践を
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。オンボーディングUIデザインが、単なる画面設計ではなく、ビジネスとユーザーを繋ぐための体系的な思考プロセスであることが、少しでも伝わっていたら嬉しいです。
それはまるで、レストランの最初の「おもてなし」のようなもの。どんなに美味しい料理(機能)があっても、最初の案内や水出し(オンボーディング)が雑だったら、お客様はがっかりして帰ってしまいますよね。
この記事で紹介した思考のステップは、どんなサービスにも応用できるはずです。
- まず、デザインの目的(KGI/KPI)を明確にする。
- 次に、ユーザーの「本音」に耳を傾ける。
- そして、最短で「Aha Moment」に導く体験を設計する。
もし、あなたのサービスで「ユーザーがなかなか定着しない」「サービスの価値が伝わっていない気がする」といった課題をお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちpicks designにお話を聞かせてください。一緒に、ユーザーが心から「使い続けたい」と思えるような、最高のおもてなしをデザインしていきましょう。