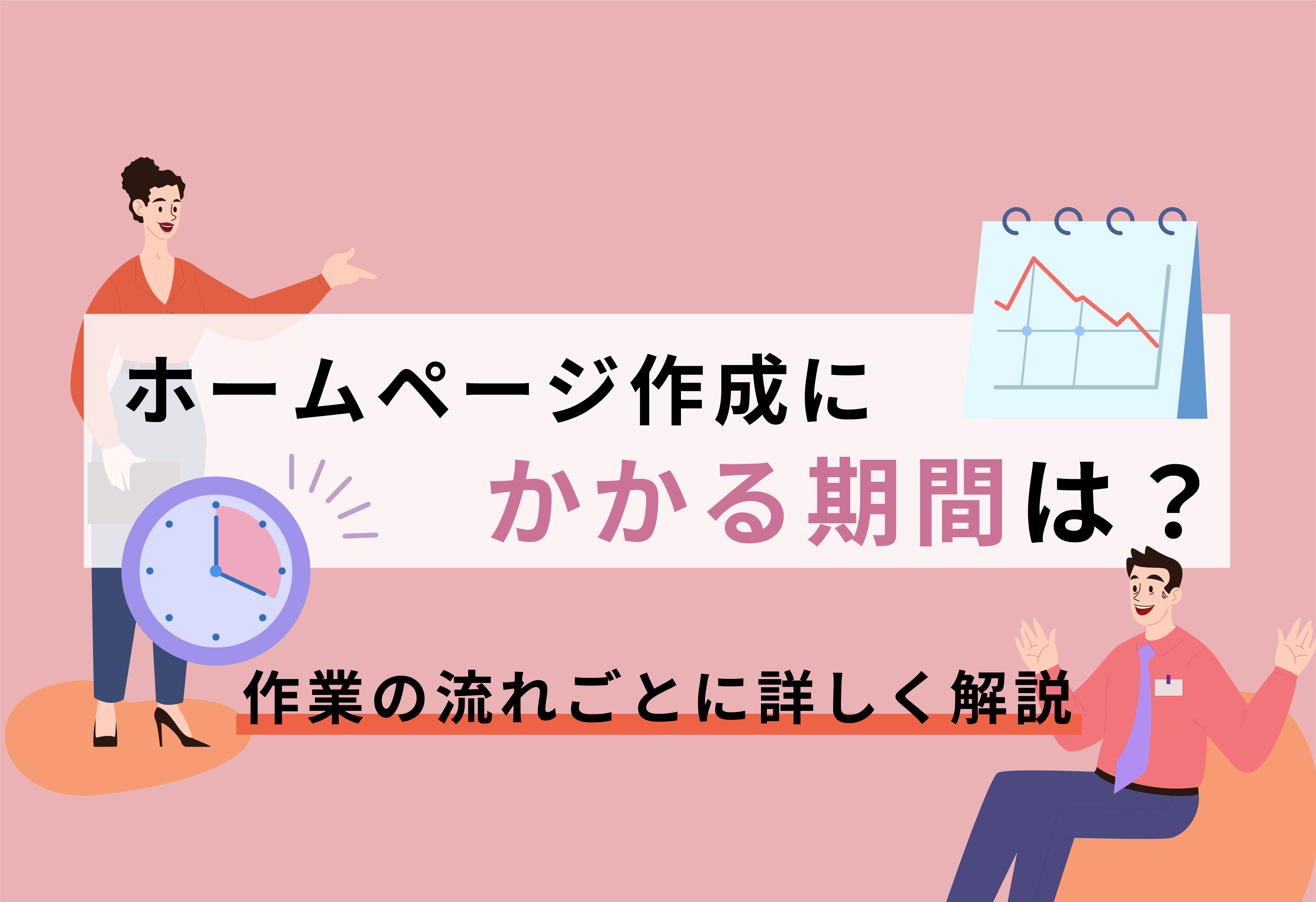「シグニファイア」はデザインをするうえで重要といわれていますが、Webサイトなどで調べても、きちんとした意味がわかりにくいですよね。
シグニファイアを理解しないまま、似た意味の「アフォーダンス」と混同してまうと、ユーザーが使いやすい、成果に繋がるデザインを作れないかもしれません。
この記事では、シグニファイアの意味や、間違われやすい「アフォーダンス」との違いを具体例と合わせて解説します。
また、シグニファイアを活用したUI.UXを高める方法についてもご紹介します。
最後まで読めば、シグニファイアを活かしたユーザーに効果のあるデザインが何かわかるので、ぜひ目を通してみてください。
目次
シグニファイアとは

シグニファイアとは、フランスの哲学者フェルディナン・ド・ソシュールが提唱した言語学上の概念で、「言葉や記号」と「その表す意味」との関係を指します。
つまり特定の言語や文化圏で「共通の意味」を持つ記号や言葉のことを指します。
分かりやすい表現として「人の行動を正しく誘導するためのサイン」を意味すると言えるでしょう。
シグニファイアの語源は「(~を)示す、知らせる、意味する」といった意味を持つ、英単語の「signify」が由来とされています。
シグニファイアは、人々の行動を制作側の意図通りにしたり、狙った感情を抱かせたりするために使われています。
水道に「水は青、湯は赤」と色で印がついていたり、銀行ATM画面で「取引開始」が少し立体的にデザインされていることで、「ここをタップすればいいんだな」と分かったりしますよね。
印やデザインがなければ、水道ではどうやって温度調節をしたらよいのかわからず、銀行ATMではどのように操作したらいいのかパッと分かりません。
人々が正しく行動できるように、デザインや効果音などを適切に使って誘導するサインをすべて「シグニファイア」と呼びます。
シグニファイアと間違われやすい「アフォーダンス」とは

シグニファイアは、もともと「アフォーダンス」という心理学の用語から生まれた言葉です。
シグニファイアとアフォーダンスは別の意味を持ちますが、デザインに関わる人のなかには両者の意味を混同してしまっている人もいます。
ここではアフォーダンスの意味やシグニファイアとの違い、2つの単語が混同されがちな理由を解説するので、両者の意味を今一度考えてみてください。
アフォーダンスの本来の意味
アフォーダンスとは、「モノ」と「人間」の間に生じる、行動における関係性を指します。
アメリカの心理学者であるジェームズ・ギブソンが、「与える、提供する」などの意味を持つ英語「afford」から造りました。
仮にAさんという人の前に椅子がある状況を例に出すと、座る、乗る、持ち上げるなど、Aさんが取る「行動の可能性」はいくつもあります。
椅子とAさんの間に生じるすべての関係性が「アフォーダンス」です。
また、アフォーダンスには「知覚されたアフォーダンス」と「真のアフォーダンス」があります。
座る、乗るなど、椅子を見た場合にAさんが思い浮かべるアフォーダンスは「知覚されたアフォーダンス」。
Aさんが気づいていなくても、振りかざす、ドアをふさぐ重しにするなど、椅子と人の間に確かに存在する関係性は「真のアフォーダンス」です。
アフォーダンスはシグニファイアのように特定の行動を誘導するものではなく、モノと人がただ存在しているだけで生じるすべての関係性を指します。
アフォーダンスが間違って広まった理由
モノと人間との間に生じる関係性を表した「アフォーダンス」は、もともと心理学用語でしたが、意味が間違ったまま広まったきっかけがありました。
『誰のためのデザイン?』の著者である認知科学者、ドナルド・ノーマンが、本の中でアフォーダンスを「物をどのように取り扱ったらよいかを判断するための手がかり」という意味で解釈したのです。
ノーマンの書籍がヒットしたことにより、「人の行動を誘導するためのもの」という間違った認識のまま、アフォーダンスがデザインの世界で広まってしまいました。
シグニファイアという言葉の誕生
『誰のためのデザイン?』の出版後、ノーマンは自分が示したアフォーダンスの概念は誤解であったと発表します。
本来のアフォーダンスと意味を区別するため、ノーマンは、「モノが人に対して与える行動の手がかり」を「シグニファイア」と呼ぶことに決めました。
扉を例にとると、押し引きやスライド、蹴破るといった関係性が「アフォーダンス」。「この扉はスライドする引き戸だ」と人に認識させるために付けた、手を引っ掛ける部分が「シグニファイア」です。
アフォーダンスがモノと人の関係性を示す「単なる情報」なのに対し、シグニファイアは人の経験や知識をもとにつくられた「意図をもつサイン」を指します。
関連:ヒックの法則とは?一見難しそうな単語をわかりやすく解説
【具体例】日常で目にするシグニファイアとは

シグニファイアは、日常のさまざまな場面で目にするものです。ここでは、シグニファイアが使われている3つの具体例を紹介します。
ドア
ドアは、シグニファイアが使われているわかりやすい例のひとつです。
ドアには押すなら触れる部分に四角い板、引くなら取っ手がついています。
タッチすることで開く自動ドアの「自動 軽くふれてください」という表示もシグニファイアです。
ドアを見たとき、人間との間には押せる、引ける、スライドで開けられる、自動で開くなどの「知覚されたアフォーダンス」がありますよね。
押し戸の場合、無数のアフォーダンスから人に「押す」という行為を選び取ってもらうため、「押す PUSH」といった表示や触れるための四角い板をシグニファイアとして活用しています。
信号機
信号機にもシグニファイアが使われています。
歩行者用の信号機を例にとると、「止まれ」は赤色、「進め」は青色または緑色。
信号機の色は、赤が一般的に危険・禁止などを連想させ、青や緑が許可・安全などを思い浮かべることを活かしています。
また、「止まれ」は止まっている人の絵、「進め」は歩いている人の絵をつけることで、「絵の通り行動すれば良い」と人の行動を誘導しているのです。
Web上のボタンやリンク
Webサイトにあるボタンやリンクにも、シグニファイアが用いられています。
例えばWebで「デザイン スクール」と調べた際、デザインスクールの公式サイトがヒットすることが多いです。
「資料請求はこちら」「無料体験を申し込む」などの立体的に見えるボタンが出てきます。
Webサイトでよく使われているリンクボタンは、ただ平面の図形+文字ではありません。
ドロップシャドウという影をつけて立体的に設計することで、「押せそうだ」と思わせ、自然にクリックすることを誘導しています。
また、Web上にリンクが貼られているとき、「公式サイトはこちら」「https://~」などの文字が青色になっていることがほとんどですよね。リンクURLが赤や緑になっていることはまずないでしょう。
インターネットを使っている人の経験上、「Web上にある青文字=他のページに飛べる」と認識しているため、リンクを青色で示すことで「わかりやすいサイトだな」と思わせているのです。
【失敗例】良くないシグニファイアとは

世の中でデザインされているもののなかには、シグニファイアが失敗している例もあります。
良くないシグニファイアを使ったデザインは、人がそれを見てどう認識するかを正しく理解できていません。
透明で何の表示もない扉が押し戸だった場合、人は「なんだ、自動ドアかと思ってしばらく待ってしまった」と時間を無駄にしてしまいます。
駐車場の空車表示が赤だったら、運転手は一瞬で「赤=満車」と思い通り過ぎてしまうでしょう。
人間がもつ一般的な常識とかけ離れていて違和感があったり、「使いづらいな」と感じさせてしまったりするシグニファイアは、適切とはいえません。
デザインをするときは、人それぞれに違う認識(知覚されたアフォーダンス)があると理解し、ターゲットに合うシグニファイアをうまく取り入れることが重要です。
デザインにおける「良いシグニファイア」とは

デザインに「良いシグニファイア」を取り入れるには、いくつかのポイントを押さえることが必要です。
ここでは、良いシグニファイアが備えている要素を解説します。
シンプルでわかりやすい
シグニファイアは、シンプルでわかりやすいことが大事です。
デザインの目的は、Webサイトのクリックなど、複数のアフォーダンスからひとつの行動を選び取ってもらうこと。
オリジナリティを出そうとしすぎて、人々の常識から遠ざかったシグニファイアをデザインに取り入れると、「操作がわかりづらい」「一瞬見間違えた」などのストレスをユーザーに与えてしまいます。
デザインをする際は、一瞬でわかりやすく、自然に行動を促せるようなシンプルなシグニファイアを組み込むことが必要です。
人々の認識を正しく理解している
良いシグニファイアは、「メンタルモデル」(人が「これはこういうものだろう」と思っていること)を正しく認識し、活用しています。
シグニファイアは人間の経験や知識にもとづいたサインのため、受け取る側の認識に個人差があるのが前提です。
たとえば、Webをよく使うマーケティング担当者向けにデザインするなら、「検索する」「メニューを開く」などの言葉を入れず、虫眼鏡の絵や「≡」「…」といった記号を用いればシンプルに表現できます。
しかしWebに詳しくないお年寄り向けにサイトをデザインするなら、「検索はこちら」「設定を変える」など文字で示してあげる必要があるでしょう。
デザインをするときは、ターゲットはどのような属性の人々で、どういった捉え方をするかを入念に考えて、シグニファイアを取り入れたほうが効果的です。
ミスリードしない
デザインにシグニファイアを取り入れる際は、見る人をミスリードしないことも重要です。
「立体的な表示はクリックできる」「青文字はリンク」などの認識があるのに、クリックできない模様を立体的にしたり、URLでない場所を青文字にしたりするのはよくありません。
「押せるかと思ったけど何もなかった」「リンクかと思ったのに違った」と人々に無意味な考えや行動をさせてしまい、違和感やストレスを与えてしまいます。
デザインをする際には、何か目的や機能があるところにシグニファイアを使い、何もないところにまるで機能があるかのような設計にしないよう注意が必要です。
シグニファイアの注意点とは?
デザインにおいても、シグニファイアは非常に重要な概念であり、以下のような注意点があります。
- ターゲットの考慮
デザインを行う際には、そのデザインが誰に向けられているのかを考慮する必要があります。
それによって、そのデザインが持つシグニファイアが受け取り手にとって適切であるかどうかを判断することができます。
- 言語や文化の違いに注意する
シグニファイアは言葉や文化に密接に関連しており、異なる言語や文化圏では異なる意味を持つことがあります。
したがって、グローバルな市場に向けたデザインを行う場合には、異なる言語や文化に対する理解が必要です。
- 色や形、レイアウトを考慮する
デザインに使用される色や形、レイアウトなどの要素は、それぞれ特定の意味を持っています。
それらの要素が持つシグニファイアを理解し、それをデザインに反映させることが重要です。
- ブランドアイデンティティの維持
デザインは、ブランドのアイデンティティを表現するための手段でもあります。
したがって、デザインを行う際には、そのブランドのアイデンティティを維持することが重要です。
- シンプルさの追求
デザインにおいては、シンプルで明快な表現が重要とされます。
複雑なデザインは、受け取り手にとってわかりにくくなることがあります。
したがって、デザインを行う際には、シンプルさを追求することが重要です。
以上の注意点を考慮しながら、シグニファイアの概念をデザインに反映させることが、より効果的なデザインを生み出すための重要な要素となります。
シグニファイアでUI.UXを高める
Webサイトやアプリ制作の際、シグニファイアの概念を活用しUI.UXを向上させる方法はあるのでしょうか?
ここではいくつかの方法をご紹介します。
- アイコンの使用
アイコンは、ユーザーが直感的に理解しやすく、認知しやすい方法で情報を伝えるために使用されます。
適切に設計されたアイコンは、ユーザーがインターフェイスをスムーズに操作するのに役立ちます。
- 言葉の選択
ユーザーに理解しやすい言葉を使用することが重要です。
適切な言葉を選ぶことで、ユーザーが操作の目的を理解しやすくなり、UI.UXを改善することができます。
- レイアウトの改善
UIデザインにおいて、レイアウトは非常に重要です。
適切なレイアウトを使用することで、情報が明確に伝わり、ユーザーが操作を行いやすくなります。
- 色の使用
色は、ユーザーに対して情報を伝えるために使用されます。
適切に色を使用することで、情報の重要性を強調したり、ユーザーがアプリケーションやウェブサイトで行うべき行動を促進することができます。
- アニメーションの使用
適切にアニメーションを使用することで、ユーザーに対して情報を視覚的に伝えることができます。
アニメーションは、UI.UXを改善するための重要なツールの1つです。
これらの方法を適切に組み合わせることで、より使いやすく、使いやすいUI.UXを作成することができます。
ただし、UI.UXは常に改善されるべきものであり、ユーザーのフィードバックに耳を傾けることも重要です。
関連:良いデザインの基準とは?実践する4つのコツを詳しく解説!
picks designにご相談下さい
Webサイト・アプリ制作をご検討の際は、picks designにご相談下さい。
picks designでは、プロが直接クライアント様のご要望をお伺いのうえ解決すべき課題を整理し最適なプランをご提案いたします。
またシグニファイアを用いたハイクオリティなデザインのご提供、UI.UXを中心とした顧客体験の強化により、ユーザー満足度の高いWebサイト・アプリ開発・運営をご依頼頂けます。
クライアント様、ユーザー様のココロを動かすデザイン思考を用いたアプリ開発を提供いたしますので、是非お気軽にご相談ください。
まとめ|「シグニファイアとは何か」がわかれば効果的なデザインができる

ここまで、シグニファイアの概要やアフォーダンスとの違い、デザインにおける効果的な取り入れ方などを解説してきました。
シグニファイアを適切に使うには、アフォーダンスを理解したうえで、ターゲットとする人間の認識を正しく活用する必要があります。
良いシグニファイアをデザインに取り入れれば、人々を意図した行動に誘導でき、売上アップやアクセス数の増加などの成果に繋がるでしょう。
シンプルでわかりやすいシグニファイアを取り入れ、人々が迷わずに行動できる効果的なデザインを目指してくださいね。
picks designでは、現在最新情報をメルマガにて配信しています。
この機会に是非ご登録ください。
→メルマガ登録はコチラ